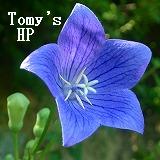幼児の歯みがき
たっくんが、ジーチャン、バーチャンの家へお泊まりした時のことだ。お風呂も済ませいよいよ寝る前になり、三人で歯みがきを始めた。
たっくんは、幼児用のハブラシ楽天 を持って、口の中へ入れ「ジー、ジー、ジー」と言いながらをみがくふりをしている。
バーチャンは、たっくんは何をしているのだろうと、漠然と思っていたらピーンときた。
「たっくん、それは電動ハブラシなの」
「うん」
たっくんの家では、電動ハブラシを使っているからね。歯みがきと言えば「ジー、ジー、ジー」と音がしないとみがいた気にならないかもね。
幼児の発想はおもしろくて、頭の固い大人が見逃していることがたくさんあるに違いない。幼児のお守りをしている人は、幼児レベルまで頭を真っさらにしてつき合う必要があると、つくづく思った。
パパの話では、歯医者でたっくんの虫歯菌の検査をしてもらったら、かなり強いタイプだったらしい。それもあって、たっくんは虫歯予防のフッ素を歯に塗ったそうだ。
パパは幼稚園の時に、かかりつけの歯科医のすすめもあり歯列矯正をした。下側の歯が上側の歯より外に出ていたためだ。小さい時の矯正は少ない時間で安くできるとのかかりつけの先生の言葉に従って、すぐに矯正してもらった。今考えてもとても良かったと思う。
たっくんは、あまり固いものはかめないが、好き嫌いはしない方だ。いろんな物を食べて栄養をもらって、大きくなってね。
一生使う歯は大事にして欲しい。歯のズキズキする痛みは本当に嫌なものだから、たっくんにはあまり経験して欲しくないなあ。
赤ちゃんの歯のはえる時期
赤ちゃんの歯の生える時期と生える順序のだいたいの目安は、下記の通りです。
生える時期や順序は個人差が大きいので、ほとんどの場合心配する必要はないようです。
| 8~9カ月 | 下の真ん中に前歯が2本 |
|---|---|
| 10カ月 | 上の真ん中に2本はえ、上下4本に |
| 11カ月~1才 | 上下4本の両側に2本ずつ、計8本に |
| 1才5~6カ月 | 奥歯(第1乳臼歯)が生え、計12本に |
| 1才7~9カ月 | 前歯と奥歯の間に犬歯が生え、計16本に |
| 2才5~6カ月 | 奥歯(第2乳臼歯)が生え、計20本に |
| 3才 | 乳歯の完成 |
永久歯の生えない乳児が10人に1人
北海道大学・昭和大学・鶴見大学・朝日大学・大阪歯科大学・九州歯科大学・鹿児島大学の付属病院小児歯科が協力して約2年間かけて調査した結果だそうです。
7歳以上の子ども1万5544人のうち1568人に永久歯の先天欠如があることが分かったそうです。乳児の方がその確率が少し高く、1割以上に永久歯の先天欠如がありました。
永久歯の先天欠如は、1、2本のケースが多いそうです。上顎の2番目の側切歯が無い、下顎の1番目の中切歯や2番目が無いというケースがよく見られるそうです。そうなると、歯並びが悪くなり、矯正をする人もいるようです。
歯が生えなのは、歯胚(しはい)が無いからだそうです。乳歯から永久歯に生え変わる頃、発育段階の開始期から増殖期に何らかの障害を受けると歯胚が形成されなくなるようです。
歯胚が作られなくなる原因は、母体の妊娠時の食生活、農薬ではと推測されてますが、はっきりとした原因は解っていないようです。
赤ちゃんの歯みがき
まだ、おっぱいやミルクを飲んでいる間は、授乳後に番茶や白湯を飲ませて口の中をきれいにしておきます。
だらだらと哺乳瓶で、ジュースや乳酸菌飲料をあげることは虫歯を作ることになるので要注意です。最初は、水でしめらせたガーゼや専用ティッシュで優しく歯と歯ぐきをマッサージしてあげてください。寝る前にすると一番効果的です。
1才をすぎたら小さい歯ブラシで、遊び心を持って楽しく口の中をゴシゴシしましょう。と言っても赤ちゃんはハブラシをしゃぶる程度しかできないので、ママの膝の上に赤ちゃんの頭を乗せて、優しく磨いてあげましょう。じっとして歯みがきができたら、大いにほめてあげてくださいね。寝る前がいちばん効果的です。
歯科医の勧める歯のケア
テレビで女性歯科医(審美歯科かな)、お名前を忘れてしまいましたが、「歯科医の勧める歯のケア」のようなものをしていました。要点をまとめてみました。
- ドライアプリコットを食べる
- 固く酸っぱいドライアプリコットは、弾力のある食べ物なのでよくかみますから、唾液もいっぱい出ます。唾液は口の中をきれいにするとともに、小さなむし歯を補修することにつながりますので、むし歯予防になります。
- 歯は磨くのではなく洗う
- 歯をゴシゴシと力まかせにこすると、歯の表面に傷が付きそこへ色やら汚れが付きます。ハブラシはペンを持つ持ち方で軽く持って、ハブラシがグラグラする状態でで磨きます。
- 色をつけないためには、綿棒でこする
- コーヒーやウーロン茶などは、歯に色素が残りやすいので、飲んだ後は早めに歯の表面を綿棒でキュキュとこするとよいです。
- ホームホワイトニングをする
- 自分用のマウスピースを作っておいて、お風呂に入っている間に、30分間歯のホワイトニングをしているそうです(歯科医の先生の場合)。アナウンサー、モデル、女優、俳優など人に見られる職業の人は、こういうケアも必要かもしれませんね。白い歯は、さわやかで、清潔感あふれて見えますから。
- 簡単ツボ押しで唾液を出す
- 唇の両端、口角と顎の中間点に唾液のツボがあり30秒押すとよいそうです。30秒も押すのですから、あまり強く押さない方がよいようです。
正しいブラッシング(歯みがき)の仕方
ブラッシング(歯みがき)は、毎日の習慣として身につけ、1回10分以上を心がけ特に就寝前のブラッシング(歯みがき)が大事です。
歯と歯の間、歯と歯肉の境は磨きにくいので、十分なケアが必要です。といっても力まかせのブラッシング(歯みがき)は、歯茎を傷めることも多いので注意が必要です。
磨き残しがないように、磨く順序を決め、1本1本、1面1面を意識しながら丁寧に時間をかけて磨きます。歯と歯が接している面はプラークが着きやすく、歯ブラシだけでは難しいので、歯間ブラシ、デンタルフロスを使って磨きます。鏡を見ながらブラッシング(歯みがき)をすると、毛先の届き具合が確認できるので効果的なブラッシングができます。
| スクラッピング法 |
|
| バス法 | 歯ブラシは鉛筆を握る要領で持ち、ブラシの先を奥歯に45度に当てて、2~3個ずつ左右に細かく往復運動をさせて汚れをかき出します |
ブラッシング(歯みがき)の到達度チェック
- 歯ブラシの持ち方は、ペングリップ状ですか?
- 歯ブラシの動きは、リズミカルですか?
- 歯ブラシ圧は、常に均一ですか?
- 腕の脇は、いつも締まっていますか?
- 歯ぐきの健康・不健康は、自分で判断できますか?
小児時からのむし歯予防
岩手医科大学 歯学部 予防歯科学講座教授の米満正美さんは、むし歯予防の3つの柱を示しています。
- フッ素を歯磨きなどでうまく使う(フッ素入り歯磨き剤を使うとよいようです)
- 正しい食生活をする(間食の取り方など)
- かかりつけ歯科医での定期的健診
東京医科歯科大学大学院 小児歯科学分野教授の高木裕三さんは、1日中間食をしているような生活をしていると、歯が再石灰化して自然にむし歯を修復していく時間がないので、むし歯が進行していくことになると言います。
また、こどもの成長過程の中で、最もむし歯ができやすい時期は、5歳と15歳だそうです。乳歯と永久歯が生えてからどちらも2~3年の時期です。生えたばかりの歯は、歯質が弱いようです。約24歳を過ぎると、新しくできるむし歯は限りなくゼロに近くなるようです。大人のむし歯は、こども時代にできたむし歯が何十年も経って大きくなったということなのだと、言います。
こども時代にむし歯予防ができれば。生涯にわたる疾患の発生予防につながるそうです。
むし歯の弊害
東京医科歯科大学大学院 小児歯科学分野教授の高木裕三さんは、こどもがむし歯で歯が抜けると、こどものアゴや顔の発達にも影響を及ぼし、発音も舌足らずになる可能性を指摘しています。
むし歯を放っておくと、全身の病気、例えばリュウマチ性の関節炎や心内膜炎などを引き起こす場合もあります。
歯周病について
歯周病とは、歯の表面につく歯垢(しこう、プラーク)細菌の塊で、炎症による出血、歯ぐきが腫れる歯肉炎、歯を支えている歯槽骨が破壊される歯肉炎があります。
入れ歯になる最大の原因は、この歯周病によるものだそうです
歯周病が恐ろしいのは、全身に及ぼす影響です。歯周病は細菌による感染症なので、その細菌や毒素が血液で全身に運ばれて、気管から肺へ入ることで体全体に悪影響を与えます。
歯周病は、糖尿病、心疾患、脳卒中、早産、肺炎などと関係があるといわれています。
歯周病になりやすい人
食生活(ベタベタと歯に付きやすい食べ物など)、糖尿病、リウマチ、薬の副作用(ホルモン製剤、抗てんかん薬、狭心症、免疫抑制剤、カルシウム拮抗剤、抗ヒスタミン剤)女性ホルモン(妊娠、更年期、思春期)ストレス、タバコ、遺伝など。
歯周病の予防
歯みがきが一番です。毎食後磨くのが理想ですが、できない方は、就寝前の歯みがきを特に念入りにされるようお勧めします。
また、歯石が付いていると、その下に歯垢が付きやすいので、歯医者さんで、歯石を取ってもらいましょう。歯石は硬くて、歯みがきでは取れません。
歯のエナメル質を溶かす飲み物
歯のエナメル質を溶かす飲み物は、飲み物のPH(ペーハー、酸性度)が、5.5以下だと溶けるそうです。中性が7.0なので、数字が小さくなるほど酸性度が強くなります。
飲み物とPH| PH | 飲み物 |
| 2.5 | 栄養ドリンク |
| 2.75 | コカ・コーラ |
| 3.18 | 三ツ矢サイダー |
| 3.3 | ワイン |
| 3.56 | アクエリアス |
| 3.58 | ボカリスエット |
| 4.03 | 果汁100%りんご |
| 4.6 | ビール |
飲み物を飲まないわけにはいかないので、だらだら飲まずにさっさと飲んで後はうがいをする。時間があれば、丁寧に歯みがき。
唾液が、酸を中和して虫歯予防に大きく貢献してくれているそうです。唾液の量と質が虫歯予防にも影響を与えるそうです。
唾液がたくさん出る人は、虫歯予防にはいいでしょうが、内服薬などの影響で唾液の量が少ない人もいます。そして、ドライマウスという病気の人も唾液が少なくなります。高齢になると老化で少なくなります。
また、唾液の質も、ホルモンバランスの変化で影響を受け、酸を中和する能力が減少するようです。